相続した株の売却にかかる税金の基礎知識

相続で取得した株を売却する際には、どのような税金がかかるのか気になる方が多いです。ここでは、売却時の課税の仕組みや計算方法について解説します。
相続で取得した株の売却益に課税される税率
相続により取得した株式を売却した場合、売却益には「譲渡所得」として課税されます。具体的には、所得税と住民税の合計で約20%が課せられます。所得税が15%、住民税が5%であり、証券会社を通じて売却するとこの税金が自動的に差し引かれることが多いです。
ただし、売却益が発生しない場合や、損失が出た場合は税金がかからないこともあります。また、NISA口座など非課税の制度を利用している場合は、一定の条件下で売却益に税金がかかりません。税金の仕組みを理解しておくことで、思わぬ負担を避けることにつながります。
株の取得費と売却価格の計算方法
株の売却益を計算する際は、「売却価格」から「取得費」と「譲渡にかかった手数料」を差し引いた額が課税対象となります。取得費は、被相続人が株式を購入した際の価格が基本となります。株式を相続したときには、購入時の証券会社の取引報告書や、過去の取引履歴が必要になります。
売却価格は、実際に株を売却した金額です。手数料については、証券会社ごとに異なりますので、明細をしっかり確認しましょう。取得費や売却価格の書類がそろっていない場合、正確に計算できず税金が多くかかってしまうこともあるため注意が必要です。
取得費加算の特例とは何か
取得費加算の特例とは、相続税を支払った場合に、その一部を株の取得費に加算できる制度です。この特例を使うことで、株式売却時の課税対象額を減らせる場合があります。
たとえば、相続税を納付した後3年以内に株を売却した場合、相続税のうち該当株式にかかった分を取得費に加算できます。手続きには相続税の申告書類や明細が必要なので、事前に準備しておくことが大切です。
\買う前にチェックしないと損!/
最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に
相続株の売却時に必要な手続きと申告の流れ

相続した株を売却するには、名義変更や申告など、いくつかの手続きが必要です。ここでは、売却までの流れや注意点を確認しましょう。
株の名義変更と売却前の準備
相続した株を売却するには、まず名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する必要があります。この手続きを「名義書換」と呼び、証券会社や信託銀行などに申請します。
名義変更の際には、戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要です。書類が揃っていないと手続きが進まないため、相続人同士で事前に準備しましょう。名義変更が完了してはじめて、株を売却できるようになります。
売却後に必要な確定申告のポイント
株を売却した翌年には、売却益があった場合に確定申告が必要です。特に、相続した株の場合は取得費や取得費加算の特例など、計算が複雑になることがあります。
証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を利用していれば、原則として確定申告は不要ですが、取得費加算の特例を利用する場合や他に譲渡損失がある場合は申告を行うことで税金が軽減されることがあります。自分のケースに合った申告方法を確認しましょう。
確定申告に必要な書類とその集め方
確定申告の際に必要となる主な書類は次の通りです。
- 取引報告書(売却時の証券会社から発行)
- 被相続人の取得費がわかる書類(購入時の取引報告書など)
- 相続税の申告書類(取得費加算特例を使う場合)
- 住民票や戸籍謄本(場合によって必要)
これらの書類はそれぞれの機関で取り寄せることができます。紛失している場合は証券会社や市区町村の窓口で再発行を依頼しましょう。書類を整理し、不明点は早めに問い合わせておくことが、スムーズな申告準備につながります。
デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!
相続した株を売却する際のトラブルと対策
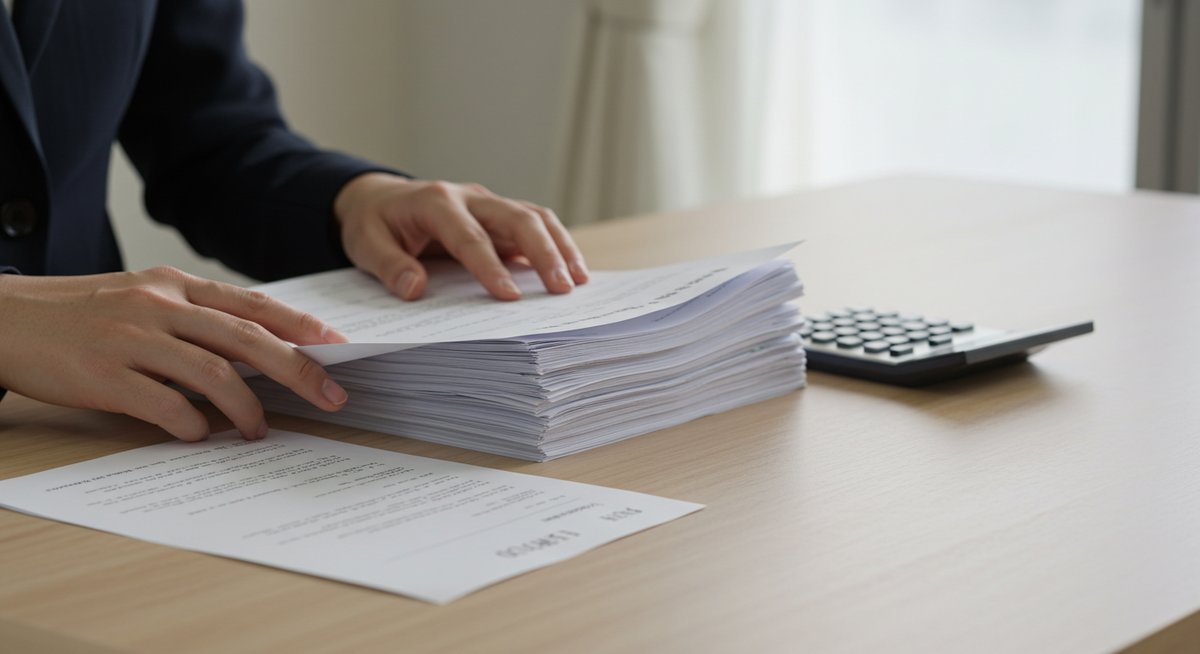
相続株の売却時には、遺産分割や売却益の分配などでトラブルが起こりやすいです。どのような問題があるのか、事前に対策を考えておきましょう。
遺産分割での株の扱いとトラブル事例
株式は現金と異なり、分割が難しい遺産です。そのため、相続人間でどのように分けるかが問題になることが少なくありません。たとえば、株をすべて一人が相続することに不満を持つケースや、株価の変動で遺産の価値に差が生じる場合があります。
また、複数人で株を共有名義にした場合、売却や配当金の受け取りに全員の同意が必要となり、意見の食い違いから手続きが進まないこともあります。こうした事例からも、遺産分割協議は慎重に進めることが重要です。
売却益の分配で生じやすい問題
株を売却した後、その利益をどのように分配するかで揉めることがあります。特に、実際の売却価格が相続時点と異なる場合や、手数料や税金の負担割合について意見が分かれることが多いです。
また、株の売却に時間がかかり、その間に株価が大きく変動することで、不公平感を訴える相続人が出ることもあります。分配に関するルールや金額の決め方を、事前に明確にしておくと安心です。
相続人間の協議を円滑に進めるコツ
トラブルを避けるためには、相続人同士の情報共有と話し合いが何より大切です。定期的に進捗状況を共有したり、専門家を交えて協議したりすることで、誤解や感情的な対立を防ぎやすくなります。
また、話し合いの際には、以下のポイントを意識しましょう。
- できるだけ全員が集まる場を設ける
- 書面で決まった内容を残す
- 不明点は専門家に確認する
冷静かつ客観的な視点で協議を進めることが、円滑な相続の鍵となります。
デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。
華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。
相続株の税金対策と節税ポイント

相続した株の売却にかかる税金を減らすための方法や、事前にできる対策について紹介します。賢く備えて負担を軽くしましょう。
暦年贈与や生前対策の活用方法
生前に株式を贈与する「暦年贈与」は、年間110万円まで贈与税がかからない制度です。これを利用して、複数年に分けて株を家族に贈与する方法があります。
また、遺言書を作成しておくことで、遺産分割時のトラブルを防ぎやすくなります。生前のうちから専門家に相談し、計画的に贈与や遺言を活用しておくことが、円滑で節税にもつながるポイントです。
不動産への組み換えによる節税策
相続した株を不動産に組み換えることで、課税評価額を抑える方法もあります。不動産は評価額が時価より低くなる場合が多く、相続税対策に有効とされています。
一例として、株式を売却し、その資金で収益用不動産を購入することで、相続税や将来の贈与税の負担を軽減できる可能性があります。ただし、不動産の購入には維持費や流動性などのリスクもあるため、計画的な判断が求められます。
専門家に相談してトラブルや損失を防ぐ方法
税金や手続きの知識に不安がある場合は、税理士や行政書士などの専門家に早めに相談することが大切です。専門家は、節税のアドバイスや遺産分割協議のサポート、必要書類の整備など、多面的に支援してくれます。
トラブルの未然防止や、余計な税金を支払ってしまうリスクを減らすためにも、複雑なケースや不明点がある場合には、プロの力を借りながら進めると安心です。
まとめ:相続した株の売却と税金対策は早めの準備と正しい知識が重要
相続した株の売却には、税金や手続きなど、事前に知っておきたいポイントがたくさんあります。早めに準備し、正しい知識を持つことで、トラブルや無駄な負担を避けることができます。
複雑に感じる場合は専門家の助けを借りながら、必要な書類や手続きをひとつずつ進めていきましょう。家族や相続人同士で協力し合い、納得できる形で相続や売却を進めていくことが大切です。
\買う前にチェックしないと損!/
最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に











