成年後見人が勝手に選任されるケースとその背景
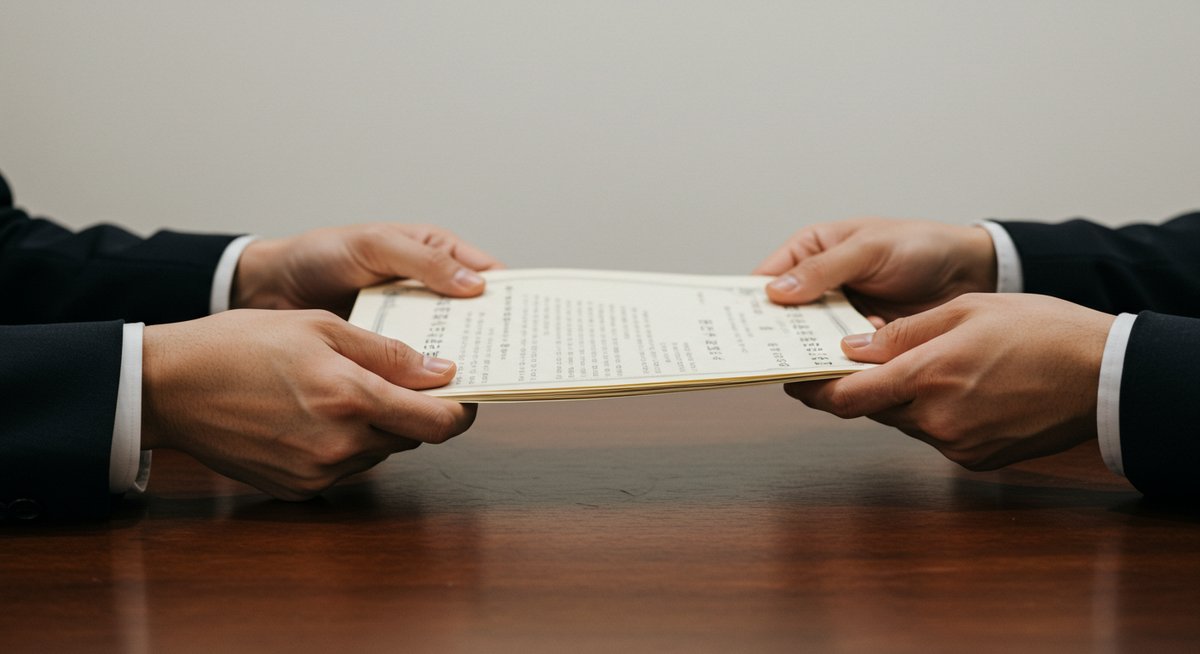
成年後見人が家族や本人の知らない間に選ばれることがあり、不安や疑問を感じる方も多いです。どのような仕組みや背景があるのか、ご説明します。
市町村長による成年後見人申立の仕組み
成年後見制度では、本人が認知症や知的障がいなどで判断力を失い、家族がいない場合や家族が申立てを行わない場合、市町村長が家庭裁判所に申立てを行うことがあります。これは、本人の権利や財産を守るために設けられた仕組みです。
たとえば、日常生活で悪質な訪問販売や不動産詐欺に遭いやすくなっている方が、適切な保護を受けられるように手続きが進められます。市町村の担当者は、医師や福祉職員からの情報をもとに、本人の状況を確認し、家庭裁判所に申立てを行う場合があります。
この申立ては「本人の利益を守る」ことを目的としていますが、ご家族が知らないうちに手続きが進むことも少なくありません。市町村長が申立てる背景には、本人の安全や福祉を守る責任があるためです。
家族や本人に無断で後見人が付けられることはあるか
成年後見人の選任は、原則として家庭裁判所の審判によって決まります。しかし、家族や本人が十分に事情を知らないまま、後見人が選ばれることもあります。
たとえば、本人が入院していたり、連絡が取れない場合や、家族が遠方に住んでいる場合、市町村が本人の保護を優先し、裁判所に申立てを行うことがあります。この場合、裁判所は必要な調査を行いますが、緊急性がある場合は速やかに後見人を決定します。
家庭裁判所から通知書が届くまで、家族が状況を把握できないこともあります。「無断で選任された」と感じるのは、手続きが迅速に進む一方で、説明や連絡が不十分なケースがあるためです。
勝手な選任を防ぐために必要な手続きと配慮
成年後見人が知らない間に選ばれることを防ぐには、家族や地域との連携、本人の意思確認が重要です。事前に意思を示しておくことも大切です。
まず、家族が日ごろから本人の状況を把握し、市町村や医療機関とコミュニケーションを取るようにしましょう。また、本人が判断力を失う前に、公正証書などを使い、自分の希望する後見人や財産管理方法を記録しておく方法もあります。
さらに、後見人選任の申立てが進められる際には、家庭裁判所から関係者に照会が行われます。通知が来た場合は、速やかに意見を伝えることが重要です。後見制度への理解を深め、備えておくことで、望まない選任を防ぐことにつながります。
\買う前にチェックしないと損!/
最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に
成年後見制度の基本と種類

成年後見制度にはさまざまな種類があり、それぞれ目的や仕組みが異なります。自分や家族に合った制度を知ることが大切です。
法定後見と任意後見の違い
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。法定後見は、本人の判断力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。一方、任意後見は本人が元気なうちに自分の信頼できる人と契約し、将来判断力が低下した場合に備える制度です。
法定後見では、裁判所が選んだ第三者が後見人になることもあり、本人や家族の希望が必ずしも反映されないことがあります。任意後見では、本人が自由に後見人を選べるため、より希望に沿った支援を受けやすい点が特徴です。
そのため、早めに任意後見契約を結ぶことで、自分の希望通りのサポート体制を整えることができます。法定後見と任意後見の違いを理解したうえで、自分や家族に合った選択肢を検討しましょう。
後見 保佐 補助 それぞれの役割
成年後見制度は、本人の判断力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。それぞれの違いを表にまとめます。
| 種類 | 判断力の状態 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 後見 | ほとんどない | 全面的な代理権 |
| 保佐 | 不十分 | 一部の代理権 |
| 補助 | 軽度の低下 | 必要な部分のみ |
「後見」は、判断力がほとんど失われた場合に利用され、後見人が財産管理や契約を全面的に代理します。「保佐」は、判断力が不十分な場合で、重要な契約などに限定して支援します。「補助」は、判断力が軽度に低下した場合で、本人の同意を得て、必要な範囲のみサポートします。
これにより、本人の状態に合わせた柔軟な支援が可能となっています。利用する際は、どの類型が適しているのかをよく考えましょう。
成年後見人の権限と責任の範囲
成年後見人には、本人の財産管理や生活を守るためのさまざまな権限があります。しかし、その分だけ大きな責任も伴います。
たとえば、後見人は本人名義の預貯金や不動産の管理・売却、必要な支払い・契約の代理などを行えますが、すべて家庭裁判所の監督下で運営されます。個人の利益が損なわれていないか、定期的に報告も求められます。
また、後見人は本人の利益を最優先に考えなくてはなりません。たとえば、自分自身や家族の利益のために本人の財産を使うことは許されません。制度の利用には、信頼関係と適切な管理が求められます。
デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!
成年後見人選任に関するトラブルとよくある誤解

成年後見人の選任や運用をめぐるトラブルは少なくありません。よくある誤解や実際の事例について解説します。
希望しない成年後見人が選ばれる理由
希望しない成年後見人が選ばれるのは、いくつかの理由があります。まず、家族間で意見がまとまらず、裁判所が中立的な第三者を選ぶ場合があります。
また、家族が遠方に住んでいる、本人の生活に直接関われない事情があると、弁護士や司法書士など専門職が選任されることも多いです。裁判所は公平性や専門性を重視するため、家族の希望があっても状況によっては第三者を選ぶ判断をします。
さらに、候補者に適格性が足りない、過去に問題があった場合なども第三者が選ばれる理由になります。家族や本人の意見が伝わりやすいように、申立てや照会の段階でしっかり希望を伝えることが大切です。
成年後見人による財産管理のトラブル事例
成年後見人が関わる財産管理のトラブルには、いくつか具体的な例があります。たとえば、後見人による不正な財産引き出しや、本人にとって必要な支出が十分に行われないケースがあります。
また、専門職後見人が選ばれた場合、報酬や手数料が高額になり、家族が負担感を覚えることもあります。後見人による生活費の管理が厳しくなり、日々の買い物や介護サービスの利用が制限されてしまうことも見られます。
このようなトラブルが起きないよう、定期的に家庭裁判所への報告義務が設けられていますが、家族も後見人の活動内容をしっかり確認し、不安な点があれば裁判所や専門家に相談しましょう。
勝手に後見人が付けられた場合の対応策
もしも希望しない後見人が選ばれてしまった場合、対応策を把握しておくことが重要です。まず、裁判所に「異議申立て」を行う方法があります。
具体的には、通知書が届いた時点で異議や意見書を提出し、理由を伝えます。たとえば「家族が後見人としてふさわしい」「本人の希望が反映されていない」といった内容です。必要に応じて、法律相談や地域の成年後見センターに助言を求めるのも良い方法です。
また、既に後見人が選任された後でも、後見人の交代や監督を求める手続きがあります。本人や家族の意見をしっかり伝えることが、納得できる後見制度利用につながります。
デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。
華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。
成年後見制度を利用しないための選択肢と対策

成年後見制度以外にも、財産管理や将来の備えに役立つ方法があります。自分や家族に合った選択肢を検討しましょう。
家族信託を利用した財産管理
家族信託は、信頼できる家族や親族に財産の管理や運用を託せる仕組みです。本人が元気なうちに信託契約を結び、将来判断力が低下した場合も家族が金融機関や不動産の手続きをスムーズに行えます。
家族信託の主な特徴は、柔軟な管理ができることと、家庭裁判所の関与が基本的に不要な点です。たとえば、家族が本人の生活費や医療費に合わせて支出を調整でき、本人の希望も反映しやすいメリットがあります。
ただし、信託契約の内容や管理方法に注意する必要があり、専門家のサポートを受けて契約を進めることが安心です。家族信託は、家族の協力が得られる場合の選択肢として有効です。
任意後見契約の活用方法
任意後見契約は、本人が元気なうちに、自分が信頼できる人と後見契約を結ぶ方法です。将来、判断力が低下したときに、あらかじめ選んだ任意後見人がサポートしてくれます。
この契約は、公正証書で作成する必要があり、家庭裁判所の監督も受けますが、本人の意思がより尊重される点が特徴です。また、任意後見人が実際に活動を開始するタイミングや、具体的なサポート内容も自由に決められます。
任意後見契約を利用することで、家族間のトラブルを防ぎやすくなり、自分らしい老後を送るための大きな備えとなります。信頼できる人を早めに選んでおくことが重要です。
成年後見制度の申立てを拒否する際の注意点
成年後見制度の申立てを望まない場合、いくつかの注意が必要です。まず、本人の判断力が十分であることを医師の診断書などで明らかにしておくと、家庭裁判所が後見開始を認めにくくなります。
また、家族や関係者が一丸となって本人の生活を支え、トラブルや不安が生じないよう日ごろから管理や見守りを強化しておきましょう。家族信託や任意後見契約など、別の制度を利用している場合も、申立てを避ける理由として有効です。
ただし、本人の財産や生活にリスクがあると判断される場合、市町村長など第三者が申立てを行うこともあり得ます。拒否を考える際は、家族だけで抱え込まず、専門家にも相談して、最適な方法を検討しましょう。
まとめ:成年後見人の選任をめぐる課題と上手な備え方
成年後見人の選任には、本人や家族の意思が十分に反映されないことや、トラブルが生じる可能性があるなど、課題が多くあります。こうした問題を防ぐためには、早めに備えを考えておくことが大切です。
家族信託や任意後見契約を活用することで、自分や家族の希望に沿った形で財産や生活の管理が可能になります。また、制度の特徴や手続きを理解し、必要に応じて専門家に相談しながら進めると安心です。
自分らしい老後や終活の準備のひとつとして、成年後見制度や代替手段をしっかり検討し、家族や地域と協力してより良い支援体制を築いていきましょう。
\買う前にチェックしないと損!/
最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に











