形見とは何か死んでいない場合でも形見になる意味と背景

形見と聞くと亡くなった方を思い浮かべますが、実は生きている人から贈られる場合もあります。形見の本来の意味や背景を知ることで、より深く大切に感じられるでしょう。
形見の本来の意味と使われ方
形見とは、もともと「故人が生前に使っていた品」を指し、亡くなった人への思い出や大切な記憶を受け継ぐ品として渡されます。この風習は、遺された家族や友人が亡くなった人を偲び、心の繋がりを感じるために続いてきました。
ですが、形見の意味は時代とともに広がり、亡くなった人の品だけでなく「大切な思い出を共有するもの」として、長く使われてきた品を譲り合う文化にも通じています。家族や親しい人への感謝や愛情がこもった品を贈ることで、「この人を大切に思っている」という気持ちを伝える手段にもなっています。
死んでいない人からの形見が意味するもの
生前に形見を渡すケースも増えてきています。たとえば高齢の方が自分の品を「思い出として持っていてほしい」と家族や友人に手渡す場面です。これは「生前贈与」と呼ばれ、気持ちを伝えるだけでなく、後のトラブルを避ける工夫としても活用されています。
また、病気や転居など人生の節目に「これまでお世話になったお礼」として贈ることもあります。生きている間に自分の希望や想いをきちんと伝えられるため、「後悔を残したくない」「自分で選んで託したい」と考える方も多くなっています。
形見と遺品の違いを知る
形見と遺品は似ているようで、意味や扱いが異なります。遺品は「亡くなった方の所有物全般」を指すのに対し、形見は「思い出や気持ちを託す特別な品物」に限定されます。
遺品は整理や片付けの対象となることが多いですが、形見は「誰かに受け継いでほしい大切なもの」として渡される点が違います。表にまとめると以下のようになります。
| 用語 | 意味 | 主な扱い方 |
|---|---|---|
| 形見 | 思い出や想いがこもった品 | 贈与・譲渡 |
| 遺品 | 故人の持ち物全般 | 整理・片付け・保管 |
\買う前にチェックしないと損!/
最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に
形見分けを行うタイミングとマナー
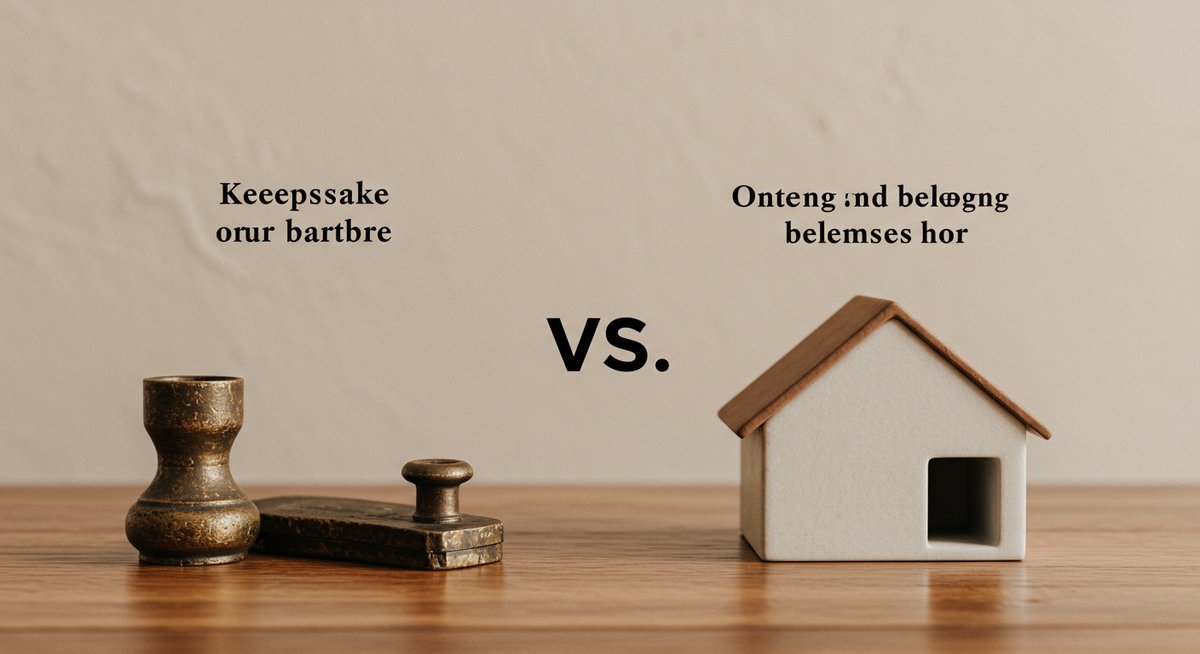
形見分けを行う時期やマナーは宗教や地域、家庭の慣習によって異なります。適切なタイミングや注意点を押さえて、大切な行事を円滑に進めましょう。
宗教ごとに異なる形見分けの時期
形見分けの時期は、宗教や宗派、地域ごとの慣習により違いがあります。たとえば仏教では「四十九日法要」を終えた後に形見分けをすることが一般的です。これは、四十九日が「故人の魂が極楽浄土に向かう節目」とされているためです。
一方、神道では五十日祭の後、キリスト教では葬儀後すぐや追悼ミサの後に行うこともあります。地域によっては「一周忌」や「三回忌」など、さらに時間をおいて形見分けをする家庭も多いです。いずれの場合も、身内や関係者の気持ちが落ち着いた時期を選ぶとよいでしょう。
形見分けのマナーと注意点
形見分けは、受け取る方の気持ちを考えることが大切です。強制的に渡すことは避け、相手の意向を確認してから贈るようにしましょう。品物の選び方にも配慮が必要です。たとえば、高価すぎるものや管理に手間がかかるものは避け、普段使いしやすいものや、思い出を感じられる品を選ぶとよいでしょう。
また、品物によっては「縁起が悪い」と感じる方もいるため、品選びの際には注意が必要です。トラブルを避けるためにも、複数人が関わる場合は誰がどの品を受け取るのか、必ず話し合って決めていくことが大切です。
生前に形見分けをする場合のポイント
生きている間に形見分けをすることは、感謝や想いを直接伝えられる大切な機会です。この場合、相手の負担にならない品を選び、気持ちを丁寧に伝えることが大切です。たとえば手紙を添えたり、品物の由来や思い出を言葉で説明したりするのもよい方法です。
また、生前形見分けは「相続」と混同されがちなので、価値の高い品や財産的な要素がある場合は、トラブル防止のためにも事前に家族や関係者と話し合いをしておくと安心です。誰に何を渡すかについて自分の意思を明確にし、記録として残しておくと、後々もめごとを避けられます。
デイサービスに人気のシニア向けカジュアルパンツ!
形見に適した品物と選び方のコツ

どんな品物が形見にふさわしいか、どのように選ぶとよいか迷うことも多いでしょう。形見に向く品や選び方のポイントを押さえておくと安心です。
形見に選ばれやすい品物の例
形見に選ばれることが多いのは、「故人や贈る人の思い出や人柄が感じられる品」です。たとえば以下のようなものがよく選ばれます。
- 時計や指輪などのアクセサリー
- 愛用していた万年筆や手帳
- 趣味で使っていた道具(釣り竿、絵筆など)
- 写真やアルバム
このような品物は、日常使いできるうえ、贈った人との絆や思い出を感じられるため、受け取った方も大切に保管しやすいです。選ぶ際は、相手の好みや生活スタイルも考慮しましょう。
形見に適さないものや避けたい品物
形見としては避けたほうがよい品物もあります。たとえば、次のようなものは注意が必要です。
- 壊れやすく管理が難しい骨董品や美術品
- 衣類や寝具など、清潔さやサイズに個人差があるもの
- 高額すぎるものや現金
また、宗教や地域によっては「刃物」や「鏡」など、縁起がよくないとされる品もあります。贈る相手や家族構成、生活環境を十分に考えて決めることが大切です。
形見を贈る相手と渡し方の工夫
形見を贈る相手は家族や親戚だけとは限りません。親しい友人やお世話になった方に託すケースも増えています。贈る際は、品物だけでなく「なぜこの品を選んだか」や「どんな思いを込めているか」を手紙や会話で丁寧に伝えると、より気持ちが伝わります。
また、直接手渡しできない場合は、宅配などで送る方法もありますが、その際も必ずメッセージを添えて気持ちを伝える工夫をしましょう。渡すタイミングや場所も、相手の都合や気持ちを考慮して決めると、良い形見分けとなります。
デイサービスや普段の習い事におすすめの男女兼用軽量トートバッグ。
華やかな柄に加え、シンプルなブラックも人気。
形見分けで起こりやすいトラブルと対策

形見分けは感情が動きやすい場面でもあり、思わぬトラブルが発生することもあります。事前に対策を知って、円満に行えるようにしたいものです。
形見分けと相続トラブルを防ぐ方法
形見分けの場で起こりやすい問題のひとつが「相続」との混同です。とくに価値のある品物や財産に近いものを形見として渡す場合は、相続争いの原因になりやすいです。
トラブルを防ぐためには、形見分けの品は何か、誰に渡すかを事前にリスト化しておき、親族間で共有しておくと良いでしょう。特に相続財産になるものは、法的なルールもあるため、専門家に相談して明確に分けることが大切です。
複数人で形見を分ける際の配慮
家族や親しい人たちが複数いる場合、「誰がどの品を受け取るか」で意見が食い違うこともよくあります。感情的にならず、平等に分けることが大切です。
話し合いが難しい場合は、以下のような方法を取り入れるとよいでしょう。
- 希望の品を事前に聞き取る
- くじ引きを利用する
- 第三者に立ち合ってもらう
こうした工夫で納得感のある形見分けができ、長く良い関係を続けやすくなります。
形見の価値や税金に関する注意点
形見分けで気をつけたいのが、品物の価値や税金の問題です。高額な品や宝石類などは、贈与税の対象となる場合があります。一般的な生活用品や思い出の品であれば問題ありませんが、高価なものを贈る場合は税務署や専門家に相談しておくと安心です。
また、「形見だから」と受け取った品が後で思わぬトラブルや負担にならないよう、価値や管理のしやすさも考慮して選びましょう。贈る側・受け取る側双方が納得できるよう、事前のコミュニケーションが大切です。
まとめ:形見の意味と分け方を知り大切な思いを未来へつなぐ
形見は、単なる品物ではなく、贈る人・受け取る人の心をつなぐ大切な役割を持っています。形見分けの時期やマナー、品物の選び方やトラブル防止の工夫を知っておくことで、より円満に大切な思いを未来へ伝えることができます。
人生の節目や別れの場面だけでなく、生きている間に感謝を伝える手段としても形見は活用できます。これから大切な人へ形見を渡す際や受け取る際は、思いやりと配慮を大切にし、自分や家族の気持ちがより豊かにつながるように工夫していきましょう。
\買う前にチェックしないと損!/
最大70%OFF!今だけ数量限定クーポンをゲットして快適な生活に











